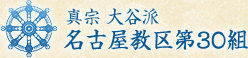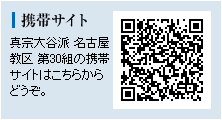仏教の基礎:釈尊の生涯
3. 釈尊の生涯
3-6 成道
「シュラマナとして」(3-4)で述べたとおり、釈尊は苦行によっては覚りを得ることができず、乳粥を食して体力を回復させ、再び菩提樹下で禅定に入ることになります。彼がアーラーダ・カーラーマとウドラカ・ラーマプトラから学んだのは精神統一でしたが、これを基礎として、これを智慧の瞑想にまで高めていきました。智慧の瞑想とは、修行初期に達成した「無所有処」や 「非想非非想処」といった境地自体を目的にするのではありません。「人々が苦悩から解放されるためにはどうすべきか」を徹底的に考え抜いたのです。 すなわち、一切の先入観を排除し、精神統一によって得られる満足感までも排除して、自己自身や世界を観察して、純粋な智慧の発動を待ちました。「血も涸れよ、肉も爛れよ、骨も腐れよ。さとりを得るまでは、わたしはこの座を立たないであろう」 (『マッジマ・ニカーヤ』9-85)との決意をもって坐り続けた釈尊は、35才にしてついに覚りをえました。そして自ら「ブッダ」(buddha、覚者)と名のりをあげました。
3-6-1 釈尊の覚りの境地
釈尊は、覚りを得た後に自らの境地を「ウダーナ」といわれる即興詩で述べています。インドでは伝統的に一夜を三区分するのですが、それぞれに対応して覚りの境地が語られています。もちろん、このテキスト自体は後世の編集ですから、釈尊がその通りに語ったという証明はできませんが、覚りに関わる重大事ですから、おおよそのところはまちがいないと思われます。
(日没時の詩 )「実にダンマ(注)が、熱心に瞑想しつつある修行者に顕わになるとき、そのとき、彼の一切の疑惑は消滅する。それは、彼が縁起の理法を知っているからである。」
(真夜中の詩) 「実にダンマが、熱心に瞑想しつある修行者に顕わになるとき、そのとき、彼の一切の疑惑は消滅する。それは、彼がもろもろの縁の消滅を知ったからである。」
(夜明けの詩)「実にダンマが、熱心に瞑想しつある修行者に顕わになるとき、彼は悪魔の軍隊を粉砕して、安立している。あたかも太陽が虚空を照らすごとくである。」
(『ウダーナ』より、玉城康四郎訳)
3-6-2 縁起の法
ここでいわれるダンマとは何でしょうか。この語はいろいろな意味を持ちますが、この場合は「縁起の法」であると言われています。「法」とは客観的真理であり、言葉によってブッダによって示される時は特に「教法」ともいいます。「縁起」とは「縁って起こること」であり、すなわち、「すべての存在はさまざまな条件(縁)によって生じる」ということを意味します。これは、仏教を他の諸々の宗教から区別する大切な点です。なぜならば、縁起の法によって示されているのは、私たちの苦悩には必ず原因があり、その原因を滅することができればおのずと苦悩の解決への道が開かれる、という合理的な思索だからです。他の宗教では、人間の苦悩は神の罰であったり宿命であったりしますが、仏教ではそうは考えないのです。
3-6-3 釈尊は何を覚ったのか
「覚る」とは「目覚める」ということですが、では釈尊は何に目覚めたのか、ということが問題です。残念ながら、文献学上はそれをはっきりさせることはできません。さまざまな説はありますが、それらはどれも主観の域を超えません。縁起の法は、あくまでも覚りをえた後に理論付されたものであり、縁起の法がただちに覚りの内容であるとはいえません。釈尊の内面を知るのは釈尊しかいないのです。
ただ、私たちはブッダ釈尊の教えを通じて仏教を理解する以外にありません。そして教えとは言語化された経典に他なりません。私たちは釈尊の言葉を手がかりとし、そこから出発する以外にないのです(独力で覚る場合は別ですが)。そして、今日誰もが認めざるを得ない釈尊の教えの最大公約数が縁起の法です。
3-6-4 十二支縁起
縁起の法についての詳細な説明は後にゆずるとして、ここではそれを展開した論理である「十二支縁起」について引用しておきましょう。
「無明によって行がある。行によって識がある。識によって名色がある。名色によって六入がある。六入によって触がある、触によって受がある。受によって愛がある。愛によって取がある。取によって有がある。有によって生がある。生によって老死・憂・悲・苦・悩・絶望がある。この苦の集積のおこりは、かくのごとくである。また、あますところなく、無明を滅しつくすことによって行が滅する。行がなくなれば識がなくなる。識がなくなれば名色がなくなる。名色がなくなれば六入がなくなる。六入がなくなれば触がなくなる。触がなくなれば受がなくなる。受がなくなれば愛が無くなる。愛がなくなれば取がなくなる。取がなくなれば有がなくなる。有がなくなれば生がなくなる。生がなくなれば老死・憂・悲・苦・悩・絶望がなくなる。この苦の集積の滅尽は、かくのごとくである」(『ウダーナ』より、増谷文雄訳)
このように、(無明)(行)(識)(名色)(六入)(触)(受)(愛)(取)(有)(生)(老死)という十二の要素から成り立つ縁起説を十二支縁起といいます。しかし、このように整った体系が成立したのは後世のことです。初期の頃はもっと単純な縁起説でした。
3-6-5 縁起説は仏教の核心
しかし初期においても、「AがあればBがある。Aが生ずればBが生ずる。AがなければBがない。Aが滅すればBが滅する」という基本形式がすでにありました。最古層に属する仏典には、その多くの例を見ることができます。ちなみに、「AがあればBがある。Aが生ずればBが生ずる」の部分を順観といい、「AがなければBがない。Aが滅すればBが滅する」の部分を逆観といいます。
十二支縁起説は後世において体系化された理論であることはたしかですが、縁起説そのものは当初から仏教の核心をなす教説でした。釈尊の十大弟子中、智慧第一と讚えられるシャーリプトラ(舎利弗)が異教の徒であった頃、「諸法は因より生じる。それら諸法の因を如来は説いた。また、それら諸法の滅をも。大沙門はこのように説きたもう」との偈頌を聞いただけで、すぐさまに釈尊への帰依を決意したとのエピソードがありますが、これによっても縁起説の重大さが理解されます。
(注)「ダンマ」はパーリ語。サンスクリット語では「ダルマ」。漢語では多くの場合「法」と訳される。
教心寺 釋眞弌